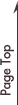枯淡(こたん)
福岡市中央区・桜坂の閑静な住宅街に佇む寿司店。店主・野口和暉さんは、福岡県糸島市で育ち、中村調理製菓専門学校で学んだ後、福岡市内で修業をスタート。その後、東京の名店「鮨 水谷」と「鮨 はしもと」で腕を磨き、2021年に28歳で独立を果たした。江戸前の技を継承しながら九州の魚に向き合い、素材の個性を見極めた一貫を追求する。凛とした静けさと柔らかな余白を併せ持つ、次世代を担う若き寿司職人だ。
平均予算:30,000円
- #桜坂
- #寿司
- #完全予約制
- #一斉スタート

平成24(2012)年/調理師科1年コース
野口和暉 氏店主
1993年、福岡県糸島市生まれ。中村調理製菓専門学校を卒業後、福岡市内の寿司屋で修業を始め、その後、東京へと拠点を移す。江戸前寿司の名店「鮨 水谷」と「鮨 はしもと」で計8年にわたり研鑽を積む。2021年、福岡・桜坂で『枯淡』を開業。精神性を重んじる江戸前の技と、九州の魚に真摯に向き合う姿勢で、独自のスタイルを静かに築き上げている。

中高と柔道をしていて、まわりには自衛官や警察官を目指す人が多かったのですが、昔から人と同じことをするのが苦手で、公務員になるというイメージも持てませんでした。どうせやるなら、職人の世界に進みたいという気持ちがあって、料理はもともと好きでしたし、カウンター越しにお客様の反応が見える仕事に惹かれたのも大きかったですね。焼鳥か寿司かで迷った末、寿司の方が格好いいと思ったんです。中学3年生のときには、すでに進路を決めていました。
――進学先をナカムラに決めた理由は?
地元・福岡のナカムラか県外の学校か迷いましたが、学費や通いやすさを考えてナカムラに決めました。高校2年生のときの進路選択で、すでに「ナカムラ」と書いていましたね。入学してからも刺激が多くて、なかでも京都と金沢への研修旅行は印象に残っています。数寄屋造りの老舗料亭での研修で、空間づくりやおもてなしを含めた“ホンモノの仕事”を体感できたことが、自分の中では大きな意味を持ちました。
――卒業後の進路について教えてください。
先生の紹介で、福岡市内の寿司屋に入りました。ただ、半年ほどで辞めてしまったんです。市場での仕入れに同行するような仕事がしたかったのですが、当時のポジションではそれができませんでした。どうせやるなら東京で江戸前寿司を学びたいという気持ちがどんどん強くなっていって。銀座の「鮨 水谷」に入りたいと思い、履歴書を持って寿司を食べに行きました。
――「鮨 水谷」では、どのようなことを学ばれましたか?
昔ながらの江戸前寿司を学びました。握りも酢飯もとてもシンプルで、つまみは基本的に刺身くらい。派手な演出ではなく、素材に余計な手を加えないスタイル。仕事の仕方も、カウンターでのふるまいも、すべてに“粋”があって、それがすごく印象に残っています。技術はもちろんですが、寿司職人としての立ち振舞や考え方が培われた時期でした。
――その後は「鮨 はしもと」へ移られたんですよね。
「鮨 水谷」の先輩に声をかけてもらったことがきっかけですね。いろいろなご縁があって、「鮨 はしもと」に入ることができました。こちらはまた違ったアプローチで幅が広がった気がします。江戸前という形式にとらわれすぎず、それでいて筋の通った寿司。技術もさることながら、精神的な部分、判断の軸を持つことの大切さを強く感じました。
――福岡で独立をしようと思ったのはなぜでしょう?
東京で独立する選択肢もありましたが、地元・糸島をはじめとする九州の魚で勝負したいという思いがありました。東京にいた頃も、実際に扱っていた魚の多くは九州産でしたし、だったら自分の足で探しながらやっていきたいなと。それに、一人っ子ということもあって、両親の近くにいられる環境で仕事ができればという思いもありました。
――寿司について、どんなスタンスで日々向き合っていますか?
「一貫でインパクトを狙う」というより、「一通り食べ終えて、明日もまた食べたい」と思ってもらえる寿司をめざしています。派手な演出ではなく、余韻に残るような寿司ですね。九州の魚は種類も豊富で、脂が強すぎない素材も多い。だからこそ、素材それぞれに適した処理を施し、酢飯と重ねていく。塩気や酸味も含めて、日々バランスを探りながら調整しています。
――これから挑戦したいことや、描いている未来について教えてください。
料理に関しては、その都度アップデートしていきたいという意識は常に持っています。その中で最近考えているのは、魚の価値や評価のされ方についてです。たとえば、アジやサバ、白子などには「この魚はこの産地」という既成のイメージがありますが、実際にはそれ以外の地域でも良い魚は獲れている。そうした“メジャー”ではない産地の価値を、料理人としてどう引き上げていくか。処理や仕立てひとつで印象は大きく変わるので、そこに可能性を感じています。漁師さんや仲買さんと情報を共有しながら、こちらから提案できるような関係性を築き、産地と食べ手の間をつなぐ存在になれたらと考えています。
――ありがとうございました。
少し厳しいことを言いますが、正直、料理を楽しめないのであれば、この道はやめておいた方がいいと思います。無理に続けても苦しいだけですし、料理を楽しむことが上達の糧になりますから。お客様にも、こちらが楽しんでいるかどうかは伝わってしまうものです。逆に言えば、自分の中に、「知りたい」「上手くなりたい」という欲があれば、自ずと前に進むことができる。料理って、その気持ちがないと続けられない仕事なんですよね。まずは、料理を楽しむこと。それがいちばん大事だと思います。