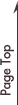一輩子吉華(イーペイズキッカ)
四川料理の名店で修業し、25歳で中国へ。帰国後、東京でいくつかの店の料理長を勤めたのち、地元・福岡で独立。本場の味を追い求め続けた先にたどり着いた、唯一無二の中国料理店。
平均予算:昼1200円、夜8000円
- #美野島
- #四川料理
- #ランチ

平成13(2001)年/調理師科2年コース
明石 圭一郎 氏オーナーシェフ
1980年、福岡県福岡市生まれ。中学生の頃から料理人を志し、高校卒業後にナカムラへ進学。四川料理の名店「吉華」の創業者であり、“四川料理の父”と称された陳建民氏の直弟子・久田大吉氏のもとで5年間に渡り修業を積む。基礎を徹底して叩き込まれたのち、25歳で中国・四川省へ渡り、現地に伝わる古典料理や手仕事の技術を体得。帰国後は首都圏で3店舗の料理長を歴任し、2023年春、『一輩子吉華』を開業。

中学生の頃から料理人になりたいと思っていました。当時はテレビ番組などの影響で料理人が注目されていた時代で、自分の努力次第で上を目指せる世界に惹かれたんです。決して裕福な家庭ではなかったので、腕一本で勝負できる道を選びたかったのだと思います。
――ナカムラを選んだ理由は?
高校卒業後は就職する予定で、四国の和食店を紹介してもらう話が進んでいましたが、直前で流れてしまって。それで学校の進路室に相談して、推薦状を書いてもらってナカムラに入学しました。まったくの予定外でしたが、結果的に行ってよかったです。楽しかったし、たくさんの出会いに恵まれました。
――在学中に印象に残っていることは?
特別に「料理人としての何かが芽生えた」とかはありませんでしたが、ただただ楽しかったです。同級生や先生との出会いに恵まれ、充実した日々を過ごしていました。同級生には料理人を続けている仲間も多く、「とぶそーや」(清川)、「肴」(警固)、「割烹すし のりを」(平尾)、「どんぶり酒場どんどん」(薬院)など、それぞれが独立して頑張っています。
――中国料理に進んだ決め手は?
本当はフレンチに行きたかったんですよ。だけど、体調を崩してしまってフランス料理店での実習に行けなくなって。その代わりに「吉華」さんに行かせていただきました。最初は3日間の予定だったんですけど、オーナーシェフの久田大吉さんの料理に衝撃を受けて、結果的には1ヶ月ほどいさせていただきました。もともと野菜が苦手だったんですけど、セロリもピーマンもニンニクの茎も全部美味しくて。「この人の料理を学びたい」って、率直に思いましたね。それが、中国料理に進むきっかけになりました。
――卒業後のキャリアを教えてください。
卒業後は、「吉華」で働かせていただきました。でも、最初は人がいっぱいで入れないって言われていたんです。2年生の夏にもう一度お願いしに行くと、久田さんから「給料は安いけどそれでもいいなら」と言っていただいて。そこから約5年間、仕事漬けの日々を過ごしました。久田さんに「いずれ中国へ行きたい」と伝えると、「行くならうちで4年は働きなさい」と言われて。基礎がないまま行っても意味がないというのが、その理由でした。包丁の使い方から火の扱い方まで、一つひとつ理論立てて教えていただきました。休みの日には料理教室に同行したり、白衣を持って先輩の店に出向いて皿洗いをしながら現場を学んだり。夜は中国語を勉強する日々でしたね。また、3年目くらいから、久田さんが料理教室に来られなくなって、自分が代わりに講師を務めることもありました。1時間半しゃべり続けないといけないから、料理の歴史や調味料の由来など徹底的に調べて臨みました。あの頃の積み重ねが、今につながっていると思います。
――中国での修業はいかがでしたか?
25歳のとき、四川省成都市に渡りました。中国料理を続けている以上、いつかは本場で学びたいという気持ちは自然に抱いていて、いわばフランス料理を志す人がフランスを目指すのと同じ感覚でした。現地では、当時もてはやされていた“新四川料理”の店に入ったんですけど、自分は古い四川料理に興味があって。「古い料理を教えてほしい」とお願いしたら、「四川には古い料理はないよ」って、最初は断られたんです。でも、どうしても学びたくてもう一度お願いしたら、「じゃあ教えてやるか」って。メニューには載っていない料理を特別に教えてもらえるようになりました。料理長曰く、「新しい料理は、古い料理の手間を省いたもの。昔の料理にこそ基礎がある」とのこと。当時はカメラとかが使えなかったので、すべてノートに記録していました。そのノートは今でも大切な財産です。
――中国へ行ってよかったと感じますか?
はい、本当に。あのタイミングだったからこそ、まだ昔の料理が残っていたんですよ。今の中国は、見た目や効率重視になっていて、そういう手仕事の料理はどんどん消えてきている。だから、自分が行けたときにちゃんと学べたのは、本当に良かったと思っています。
――帰国後は?
父の体調が悪くなり、一度福岡に戻りました。そのあと父が亡くなって。落ち着いたころに、もう一度「吉華」に戻ったんです。久田さんからは「店を継がないか」と声をかけていただきましたが、自分の中では、「まだやれることがある、もっとやりたいことがある」と思っていたので、申し訳ないけど、断らせてもらいました。それから東京で2店舗、千葉で1店舗、計3店舗で料理長をしました。立ち上げからメニュー開発、人材育成まで幅広く任されて。現場にも立ち続けていたので大変でしたが、自分の視野が広がるいい経験をさせていただきました。
――独立することになった経緯を教えてください。
2019年に福岡に戻ってきたものの、すぐにコロナ禍に突入。物件も見つからず、正直「もう自分の店は無理かもしれない」と感じていました。そんなとき、福岡・美野島で「巴蜀」をされていた荻野さんから、「自分は東京に行くので、よかったらこの場所でやってみませんか?」と声をかけていただいたんです。
最初は迷いましたが、「お客様もついていて、売上も安定しています。ここでできなかったら、ほかでもできないと思う。同じ気持ちを持った料理人に引き継いでほしい」と言っていただいて、心が動きました。「自分が店を持つなら、人と人とのつながりを活かせる場所がいい」と以前から思っていたので、このご縁に背中を押されるかたちで、ここでの独立を決めました。
――お店のコンセプトは?
いわゆるうま味調味料は、完全に使わないというわけではありませんが、極力使わない方向で考えています。塩と油、それから香辛料と素材の香り──それをどこまで引き出せるかというのが自分のスタンスですね。香辛料って、火入れや合わせ方で印象が全然変わるんですよ。だから、一つひとつの工程を丁寧に積み重ねていくことが大事だと思っています。調味料の多くは、今でも自分で中国へ足を運び、自分の目で確かめて買い付けています。香りが合わないと、うちの料理には合わないので。派手さよりも、「また食べたくなるな」と思ってもらえるような料理が理想ですね。お昼はランチセットが中心で、夜はご紹介で来店される方が多いです。夜は予約制のコースをご注文いただくことが多いですが、アラカルトのメニューもご用意しています。お客様との距離も心地よくて、緊張感を持ちながらも、自分らしくいられる空間です。
――今後の展望を教えてください。
大きな目標というよりは、「今を継続していけたら」って気持ちですね。体力がある限り、現場で料理と向き合い続けたいです。理想を言えば、夜の営業は将来的に予約制のコースのみで成り立つような形にしていきたいと考えていますが、現時点では通常の予約方法で、コース・アラカルトいずれにも対応しています。自分のことを理解してくれているお客様が自然と集まってくれる──そういう信頼の循環が理想ですね。その一方で、中国にはこれからも定期的に通い続けたいと思っています。学ぶというより、中国の友人たちと過ごす時間の中で、文化としての食を改めて感じ続けたいというのが大きいです。また、いろんな方とのコラボレーションも積極的に続けていきたいと思っています。ワインは「ラタフィア」(薬院)の吉村智美さんにお願いしているんですけど、料理への理解が深くて、セレクトも素晴らしいんです。これまでにも、吉村さんとペアリングのイベントなどをご一緒させていただいていますが、そういった取り組みは自分にとっても新しい刺激になりますし、店にもいい風を吹き込んでくれる。さまざまなジャンルの料理人やソムリエの方々とも、今後いろいろなカタチでご一緒できたらと思っています。
――ありあがとうございました。
「この料理が好きだから」というより、「この人についていきたい」と思える人と出会うことが大事なのかなと思います。自分の場合は、なんだかんだ厳しかったですけど、最終的には久田さんの温かさに支えられて、ここまで続けてこられました。ほかの店だったら、多分続いていなかったと思います。どれだけ覚悟があっても、続けられるかどうかは、人との出会いに左右される部分がすごく大きい。学生のうちに「この人に教わりたい」「この人だったら、どんなに厳しくされても納得できる」と思える人に出会うこと。そのためには、とにかく出会う機会をたくさんつくること。それが、この仕事を長く続けていくうえで、すごく大事なことだと思います。