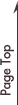ひら田
唐津市中心部、旧城下町の一角に佇む日本料理店。「美山荘」(京都)や「さ乃」(福岡・朝倉市)などで研鑽を重ねた平田智隼さんが、ご夫婦で営む。地元の山海の恵みを用い、季節感と茶の湯の精神を大切にした料理を提案する。
平均予算:昼8000円、夜10000〜15000円
- #唐津
- #佐賀県

平成7(1995)年/調理師科1年コース
平田 智隼 氏店主
1976年、福岡県大刀洗町出身。ナカムラを卒業後、中村学園事業部を経て、唐津の日本料理店で約5年間修業。茶道との出会いをきっかけに、「うつわ料理 さ乃」(福岡・朝倉市)や「美山荘」(京都)で経験を重ねる。2016年に唐津で独立し、『ひら田』を開業。2022年、現在の店舗に移転。茶の湯の精神を軸に、季節の料理を夫婦で丁寧に届けている。

家族や親戚に料理関係の仕事をしている人はいませんでしたし、特別何かに影響を受けたわけでもありませんが、中学生のころから料理は嫌いではありませんでした。身近に料理人がいないからこそ、むしろ「誰もしていないことに挑戦してみよう」という気持ちが芽生え、「料理の道もいいかもしれない」と思ったことがきっかけです。
――ナカムラを選んだ理由は?
基礎を身につけたあとは、できるだけ早く現場に出たいという思いがあり、1年制のコースがある学校を探していました。いくつかの学校のパンフレットを見比べる中で、もっとも惹かれたのがナカムラでした。雰囲気や講師の顔ぶれ、授業内容にも魅力を感じたんです。結果的に、座学や実習を通して基礎をしっかり学べたことは、現場に出てから本当に役立ちました。
――在学中、印象に残っていることはありますか?
西洋料理・日本料理・中国料理と一通り学べるのがナカムラの特徴です。最終的に、自分に合っていて長く続けられると思った日本料理を選びましたが、在学中に他ジャンルを学べたことが、今の自分の引き出しを広げてくれたと感じています。
――卒業後の進路について教えてください。
高校生のころからヘルニアを患っていて、長時間の勤務に不安があったため、先生に相談したところ、勤務時間が安定している中村学園事業部への入社を勧められました。学校や企業の食堂、病院などに配属され、規模や環境によって異なる段取りや仕事の進め方を学べたことは、貴重な経験でしたね。その後、やはり日本料理の道に進みたいと思い、再び先生に相談したところ、特別講師として来られていた方が営む唐津の日本料理店を紹介され、約5年間修業させていただきました。ここで土地の魅力や地元の食材の素晴らしさに触れたことが、のちに唐津で独立する大きなきっかけになりました。
――茶道や茶懐石に関心を持たれたきっかけは?
唐津での修業を終えて実家に戻ったあと、少し立ち止まる時間がありました。そのとき、「日本料理を続けていくうえで何か足りない」と疑問に感じ、思い至ったのがお茶の世界でした。25歳のころからお稽古に通い始め、学ぶうちに茶懐石にも強く惹かれていきましたね。あるとき、茶懐石を提供する「うつわ料理 さ乃」さんに伺ったことがきっかけで、「ぜひ学ばせてほしい」とお願いし、押しかけるような形で、2年弱働かせていただきました。
――その後はどのような道を?
「さ乃」さんでの経験を通じて、旬の野菜や山菜など、自然の恵みを活かした料理の楽しさと奥深さに改めて惹かれるようになりました。もっと自然に近い場所で、その感覚を深めたいと思い、京都の「美山荘」さんで3年ほど修業。摘草料理で知られる宿で、朝は山に入り、採ってきた山菜で料理を組み立てるという日々。自然の中にあるものをどう料理にするか、その感覚を体で覚えていったように思います。
――独立に至るまでの経緯を教えてください。
唐津に戻ってきたのが、32歳のとき。かつて働いていた日本料理店に再び入り、7〜8年ほど勤めました。その後、2016年に40歳で『ひら田』を開業。2022年11月に現在の場所へ移転しました。
――『ひら田』はどのようなお店ですか?
昼夜ともに完全予約制のコースのみで、自分たちにできる範囲の仕事を、夫婦ふたりで丁寧に向き合いながら進めています。コースの締めくくりには、自家製の菓子とお薄(お抹茶)をお出しするのが習わしです。お茶を点てる時間は、お客様と正面から向き合う、静かで大切なひととき。派手な演出はありませんが、素材や器とまっすぐに向き合える空間づくりを大切にしています。
――料理をするうえで大切にしていることは?
どこで何をしていても、自分は一料理人であり、ものづくりに携わる人間であるという意識を常に持ち続けています。言葉の使い方や日々の行動も、すべて料理に表れると思っていて。気の緩みや甘えは、必ず料理にも出てしまう。だからこそ、日頃の言動には細心の注意を払い、仕入先の方やどんなに近しい存在の方に対しても、感謝の気持ちを忘れず接するよう心がけています。
――今後の展望を教えてください。
店を大きくしたいという考えはありません。出張の茶事なども含めて、小さな店だからこそできることを大切にしながら、長く続けていける、長く愛され続ける店でありたいですね。流行に左右されることなく、「また食べたい」「ここに来るとホッとする」と思っていただけるような、変わらない安心感を届けていきたいと思っています。一方で、日本料理は世界的にも注目を集めています。私たちの料理を通して、日本の文化や季節の移ろいを丁寧に伝えていくことが、自分の役割だと感じています。
――ありあがとうございました。
学校でしか学べないことは、本当にたくさんあります。今ある時間を大切にして、現場に出てから役に立つ土台をしっかり築いてほしいですね。そして最終的には、自分を信じること。私も「いつか店を持ちたい」と思いながら、実現までに20年かかりました。思い続けることが、何よりの原動力になると思います。頑張ってください。